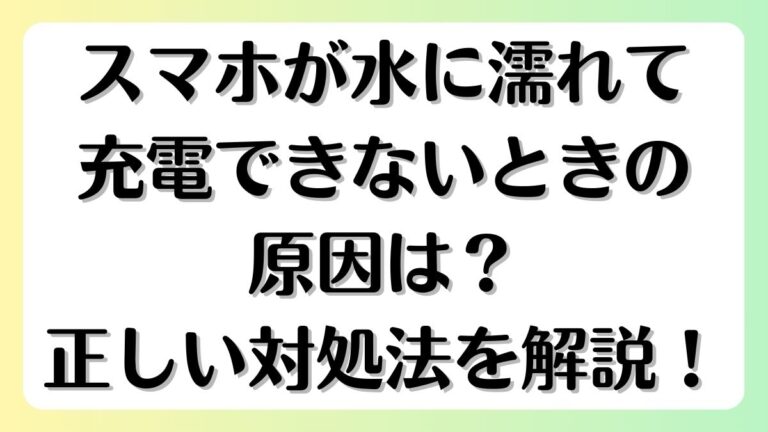「スマホが水に濡れて充電できない」そんな経験をしたことはありませんか?
突然の雨やうっかり水をこぼした瞬間、スマホが反応しなくなると本当に焦りますよね。
実は、スマホが水に濡れて充電できなくなるのは、内部の安全機能や水分残りが原因で起こることが多いんです。
この記事では、スマホが水に濡れて充電できないときの原因と正しい対処法、そして絶対にやってはいけない行動まで、わかりやすく解説します。
さらに、修理やデータ復旧の方法、防水対策までしっかり紹介しているので、この記事を読めば今後のトラブル予防にも役立ちます。
大切なスマホを守るために、ぜひ最後までチェックしてくださいね。
スマホが水に濡れて充電できないときの原因

スマホが水に濡れて充電できないときの原因について解説します。
それでは、それぞれの原因を詳しく見ていきましょう。
水分が充電端子に残っている
スマホが水に濡れて充電できない原因の多くは、充電端子(LightningやUSB-Cポートなど)に水分が残っていることです。
充電端子の中にわずかな水滴があるだけでも、金属部分が通電してショートを起こし、充電ができなくなります。
最近のスマホは安全設計になっていて、水分を検知すると自動的に充電を止める仕組みがあります。
これはショートや発熱を防ぐための機能です。
そのため、水に濡れた状態で「充電が反応しない」と感じても、それはむしろ正常な動作です。
焦って無理にケーブルを挿すのは避けてください。
見た目が乾いていても内部には微量な水分が残っていることがあります。
数時間から半日程度、風通しの良い場所で自然乾燥させると良いです。
内部の回路がショートしている
もしスマホ内部に水が入り込んでしまった場合、基板や電子回路がショートしてしまうことがあります。
スマホの内部はとても繊細で、わずかな水分でも回路間の導通を起こし、電流が異常な経路を通ることで故障につながります。
一度ショートしてしまうと、内部のチップや部品が焼けてしまい、電源が入らなくなったり、充電が一切できなくなったりします。
この状態では自力での修理は難しく、早めに修理店やメーカーに相談するのが賢明です。
特に塩水や飲み物などが混ざった液体に濡れた場合は腐食が進みやすく、時間が経つほどダメージが拡大するので注意が必要です。
バッテリーやケーブルが故障している
水がかかったことで充電できないとき、実はバッテリーやケーブルが壊れているケースも多いです。
特に充電ケーブルは断線や内部腐食が起こりやすく、濡れた状態で使うとすぐに劣化してしまいます。
また、水分が原因で充電回路が過熱し、バッテリーが過放電を起こして充電を受け付けなくなることもあります。
純正のケーブルや新しいアダプターを試してみても改善しない場合は、内部バッテリーがダメージを受けている可能性があります。
その場合は無理に電源を入れず、修理店に持ち込むのが安全です。
充電ポートの異物や錆が原因
水に濡れたあとに乾燥が不十分だと、充電ポートに錆や白い結晶(塩分の析出物)が残ることがあります。
この錆や結晶が端子との接触を妨げ、ケーブルを挿しても通電しなくなります。
また、水の中に含まれる不純物が原因で端子が変色したり、腐食してしまうこともあります。
無理に綿棒や金属を入れて掃除すると、かえって内部を傷つけてしまう危険があります。
清掃が必要な場合は、修理店でのクリーニングを依頼するのが安心です。
湿気が多い季節や水回りでスマホを使う人は、定期的にポートをチェックする習慣をつけましょう。
スマホが水に濡れて充電できないときの正しい対処法

スマホが水に濡れて充電できないときの正しい対処法について詳しく解説します。
焦って充電しようとすると、かえってスマホを壊してしまう可能性があります。
落ち着いて、以下の手順を行ってください。
電源を切ってすぐに乾かす
まず最初に行うべきことは、電源をすぐに切ることです。
電源が入ったままだと、水分が内部に入り電流が流れることでショートを引き起こしてしまう恐れがあります。
電源を切ったあとは、タオルやティッシュなどで外側の水分を軽く拭き取ります。
このとき、強くこすったり、端子部分を押し込むように拭くのは避けてください。
外側の水を拭き取ったら、できるだけ早く乾かす準備をしましょう。
自然乾燥でもよいですが、スマホを立てて置くと内部の水分が下にたまりにくく、乾きやすくなります。
また、扇風機の風を弱く当てるのも効果的です。
熱風を使うのではなく、常温の風でゆっくり乾燥させることがポイントです。
この段階では絶対に電源を入れ直したり、充電を試したりしないようにしてください。
内部が完全に乾くまでは時間をかけましょう。
充電ケーブルを挿さない
スマホが濡れた状態で充電ケーブルを挿すのは絶対に避けてください。
水分が端子に残っていると、通電によってショートが発生し、スマホやケーブルが故障する恐れがあります。
実際、最近のiPhoneやAndroid端末では「水分を検出しました」という警告が表示され、充電が自動的に止まる仕様になっています。
これは安全のために設けられた保護機能です。
警告が出た場合は焦らず、時間をおいて乾燥させてください。
何度もケーブルを抜き差しするのは逆効果で、内部を傷つけるリスクがあります。
もし警告が出ないタイプのスマホであっても、少なくとも6時間以上は充電を試さないようにしましょう。
完全に乾燥していれば問題ありませんが、「ちょっとくらいなら大丈夫」と思って挿すのは非常に危険です。
SIMカードやケースを外す
次に、SIMカードトレーやスマホケースを外しておきましょう。
これらの部分には水がたまりやすく、乾燥を妨げる原因になります。
SIMカードスロットの中は金属端子があり、濡れたままだと腐食やショートを起こしやすくなります。
SIMカードやmicroSDカードは取り出してティッシュなどで水分を拭き取り、別の乾いた場所に保管してください。
スマホケースも内部に水が残りやすいため、取り外してケースの内側までしっかり乾かします。
とくに防水ケースを使っていた場合は、内部に湿気がこもっていることがあるので、開けて空気を通すことが大切です。
自然乾燥や乾燥剤で水分を取る
乾燥の方法としては、自然乾燥が最も安全です。
常温で24時間以上放置することで、内部の微細な水分まで蒸発します。
ただし、湿度が高い場所だと乾きにくいため、風通しの良い場所に置くか、除湿剤の近くに置くとよいです。
乾燥剤(シリカゲル)を使うのも効果的です。
スマホを密閉できる袋やタッパーに入れ、乾燥剤を一緒に入れておくと水分が吸収されやすくなります。
昔から「お米の中に入れると良い」と言われることもありますが、最近ではおすすめされていません。
お米の粉が内部に入り込むリスクがあるためです。
乾燥後も水分が完全に抜けたか分からない場合は、充電を試す前に修理店で点検してもらうのが安心です。
スマホが水に濡れた後に絶対にやってはいけない行動

スマホが水に濡れた後に絶対にやってはいけない行動について詳しく解説します。
「早く乾かしたい」「電源が入るか試したい」と思う気持ちは分かりますが、間違った行動をすると内部の損傷が進んでしまいます。
ここでは、やってはいけない代表的な行動を一つずつ見ていきましょう。
ドライヤーで乾かす
最も多い誤解が、ドライヤーで乾かすという方法です。
熱風で乾かすと確かに表面の水分はすぐに飛びますが、内部に熱がこもり電子部品を傷めてしまう危険があります。
スマホの基板やバッテリーは熱に非常に弱く、特に50℃を超えると接着剤や絶縁素材が劣化してしまいます。
さらに、熱風を吹きかけると内部の水分が奥へ押し込まれてしまい、逆に乾燥を妨げることにもつながります。
安全に乾かしたい場合は、常温での自然乾燥または乾燥剤を使う方法がベストです。
焦って熱を加えるよりも、「時間をかけて完全に乾かす」ことが何より重要です。
充電を試す
濡れた状態で「電源が入るか確認したい」と思って充電ケーブルを挿すのは、絶対にやってはいけません。
充電端子内に水分があると通電によってショートが発生し、内部の回路やバッテリーを一瞬で破損させることがあります。
特にiPhoneなどでは、水分を検知した際に「充電はできません」という警告が出ることがありますが、これはまさに危険を防ぐための機能です。
警告が出ない古い機種の場合は、本人が気づかないうちに内部でショートしていることもあります。
完全に乾くまで充電は我慢し、少なくとも12時間以上は時間をおくようにしましょう。
振るや叩くなどして水を出そうとする
スマホを強く振ったり、叩いたりして水を出そうとする人もいますが、これは非常に危険です。
内部の配線や接続部分は非常に繊細で、衝撃を与えると簡単に接触不良や断線を起こしてしまいます。
また、振ることで水がスマホの上部やスピーカー部分に移動し、より深い場所まで入り込んでしまうこともあります。
中には「スピーカーから音が出なくなった」と相談する人もいますが、その多くはこのような行動が原因です。
内部に水が入っている場合は、動かさずに落ち着いて乾かすことが一番の対処法です。
電子レンジやヒーターで温める
ネット上で「電子レンジで温めたら直った」などという誤った情報を見かけることがありますが、これは絶対に真似してはいけません。
電子レンジやヒーターでスマホを温めると、内部のリチウムイオンバッテリーが過熱して発火や爆発の危険があります。
スマホの構造は高温に耐えるようには作られていません。
基板が焼け、プラスチックが溶ける可能性もあります。
また、温風ヒーターの近くに置くだけでも内部温度が上昇し、内部部品が劣化してしまいます。
安全に乾かすためには、常温の自然乾燥を徹底し、決して熱源を使わないことが鉄則です。
スマホが水に濡れて充電できないときの修理方法

スマホが水に濡れて充電できないときの修理方法について解説します。
濡れたスマホは、正しい手順で対応すれば復旧するケースも多いです。
ただし、修理に出すタイミングや方法を間違えると、直せるものも直らなくなることがあります。
修理に出す前に確認すること
修理に出す前に、まず確認しておきたいのは「水没マーク」の状態です。
多くのスマホには、水に濡れたかどうかを判断するための小さなシールが貼られています。
このマークが赤く変色していれば水没の証拠であり、メーカー保証が適用されないことがあります。
また、スマホが乾燥してから電源を入れても動かない場合は、内部の基板やコネクタが損傷している可能性が高いです。
その場合は自分で分解しようとせず、早めに修理店へ持ち込みましょう。
分解してしまうと、修理対応が受けられなくなるリスクもあります。
修理依頼の前に、「データをどう扱ってほしいか」も伝えるようにしましょう。
初期化が必要な場合もあるため、重要なデータが残っている場合はデータ復旧も同時に相談すると安心です。
メーカー修理と街の修理店の違い
スマホの修理には、大きく分けて「メーカー修理」と「街の修理店(非正規店)」の2種類があります。
それぞれの特徴を理解して選ぶことが大切です。
| 項目 | メーカー修理 | 街の修理店 |
|---|---|---|
| 対応範囲 | 正規の基板・バッテリー交換、保証対応 | 基板洗浄や部分交換など柔軟な対応 |
| 修理スピード | 数日〜1週間程度 | 即日修理が可能な場合もある |
| データ保持 | 基本的に初期化される | データを残したまま修理できる場合が多い |
| 費用 | 1〜5万円程度(保証外の場合) | 5千円〜2万円程度(内容による) |
メーカー修理は安全性と信頼性が高いですが、データが消えることが多く、期間もかかります。
一方、街の修理店は柔軟で即日対応してくれることもあり、水没後の洗浄処理なども行ってくれます。
ただし、非正規修理を行うとメーカー保証が無効になる場合もあるため、データ優先か保証優先かを明確にして選びましょう。
修理費用の目安と保証対応
水没によるスマホの修理費用は、故障箇所や損傷の程度によって異なります。
| 故障箇所 | 修理費用の目安 |
|---|---|
| 軽度の水没(クリーニングのみ) | 5,000〜10,000円前後 |
| 基板修理やバッテリー交換 | 10,000〜25,000円程度 |
| 重度の水没(電源不良・起動不可) | 30,000円以上かかることも |
キャリアやメーカー保証が有効な場合は、修理費用が無料または大幅に安くなることもあります。
ただし、水没は「過失」とみなされるため、保証の対象外になるケースが多いです。
AppleCareやキャリアの「スマホ補償サービス」に加入している人は、自己負担を抑えて交換できる場合があるので、契約内容を確認しておきましょう。
データ復旧の可能性と依頼先
スマホが水没して電源が入らなくなっても、データが完全に消えたわけではありません。
内部のストレージチップが無事であれば、専門業者によってデータ復旧が可能です。
特に写真、LINE、連絡先などはチップから直接読み出すことができる場合があります。
ただし、基板がショートしている場合は難易度が上がるため、できるだけ早く専門のデータ復旧業者に依頼することが重要です。
復旧費用の目安は、軽度で1〜3万円、重度の場合は5万円以上になることもあります。
水没後に電源を何度も入れようとしたり、充電を試したりすると復旧率が下がるので、できるだけ早い段階で依頼するのがポイントです。
スマホが水に濡れて充電できなくならないための予防策

スマホが水に濡れて充電できなくならないための予防策について解説します。
スマホの水濡れトラブルは、一度でも起きると修理費用が高くつきます。
日常のちょっとした工夫で防げることも多いので、以下の予防策をしっかり覚えておきましょう。
防水ケースやポーチを使う
最も効果的な予防策は、防水ケースやポーチを使用することです。
スマホを完全に覆うタイプの防水ケースなら、プールや海辺、雨の日でも安心して使えます。
最近では透明なタッチ対応タイプも多く、ケースに入れたまま操作できるので便利です。
ただし、防水ケースにも「防水等級」があります。
IPX5やIPX7などの表示を確認して、利用シーンに合ったものを選びましょう。
防水ポーチを使う場合は、開閉部分の密閉が甘くなっていないか定期的に確認してください。
1回の水没で数万円の修理費用がかかることを考えると、防水ケースは非常にコスパの良い投資です。
防水性能の高いスマホを選ぶ
次に、スマホそのものの防水性能をチェックして選ぶことも重要です。
最近のスマホには「防水等級(IP規格)」が設定されています。
| 等級 | 防水性能の目安 |
|---|---|
| IPX4 | 水の飛まつに対して保護される(小雨程度) |
| IPX7 | 一時的な水没にも耐えられる(1m深さで30分) |
| IPX8 | 継続的な水没にも耐えられる(メーカー定義) |
IPX7以上のスマホであれば、軽い水濡れや一時的な水没にも耐える設計になっています。
ただし、防水とはいえ完全防水ではありません。
時間が経つにつれて防水パッキンが劣化するため、過信しすぎないことも大切です。
定期的にメーカーで防水チェックやメンテナンスを受けると、性能を長持ちさせることができます。
お風呂やキッチンでの使用を避ける
スマホの水濡れ事故の多くは、お風呂やキッチンでの使用時に発生します。
特にお風呂の湯気は、目に見えなくてもスマホ内部に入り込みやすいです。
高温多湿な環境では、内部の結露が発生し、徐々に端子や基板にダメージを与えることがあります。
また、キッチンでは調理中の水はねや油の飛び散りなどがスマホの充電口に入り込み、通電トラブルを起こす原因になります。
スマホを使う必要がある場合は、防水スタンドやタブレットホルダーなどを利用して、直接濡れないようにする工夫をしましょう。
「ちょっとだけなら大丈夫」と思って使うのが一番危険です。
日常的にリスクを避ける意識を持つことが大切です。
定期的に充電口の清掃を行う
最後に、充電口の清掃を定期的に行うことも効果的な予防策です。
ほこりや皮脂がたまると水分を吸いやすくなり、錆や腐食の原因になります。
清掃するときは、柔らかい歯ブラシやエアダスターを使い、優しく汚れを落としてください。
金属製のピンや針などを使うのは厳禁です。内部の端子を傷つけてしまう危険があります。
また、防水スマホでもゴムパッキンの部分に汚れが付着すると防水性が落ちるため、綿棒で優しく拭き取ると良いです。
定期的なメンテナンスを行うことで、急なトラブルを防ぎ、スマホを長く安全に使い続けることができます。
まとめ|スマホが水に濡れて充電できないときの最善の行動
| 対処法 |
|---|
| 水分が充電端子に残っている |
| 内部の回路がショートしている |
| バッテリーやケーブルが故障している |
| 充電ポートの異物や錆が原因 |
スマホが水に濡れて充電できないときは、焦らず落ち着いて対応することが大切です。
まずは電源を切り、充電ケーブルを挿さずに自然乾燥させることが最優先です。
濡れたまま充電したり、ドライヤーで乾かしたりするのは絶対に避けましょう。
内部の回路がショートして修理不能になるリスクがあります。
乾燥後も電源が入らない場合は、無理に操作せず、修理店やメーカーへ早めに相談してください。
状態によってはデータ復旧も可能です。
そして、今後同じトラブルを防ぐためには、防水ケースの使用や定期的な充電口の清掃など、日常的な予防が欠かせません。
「スマホが濡れて充電できない」という状況は誰にでも起こり得ますが、正しい知識を持っていれば被害を最小限に抑えることができます。
一度でも水に触れた場合は、「乾かしてから確認する」という行動を忘れないようにしましょう。
スマホの安全性や修理対応については、各メーカーの公式サポートページを確認するのもおすすめです。
以下のリンクから最新情報を参照できます。