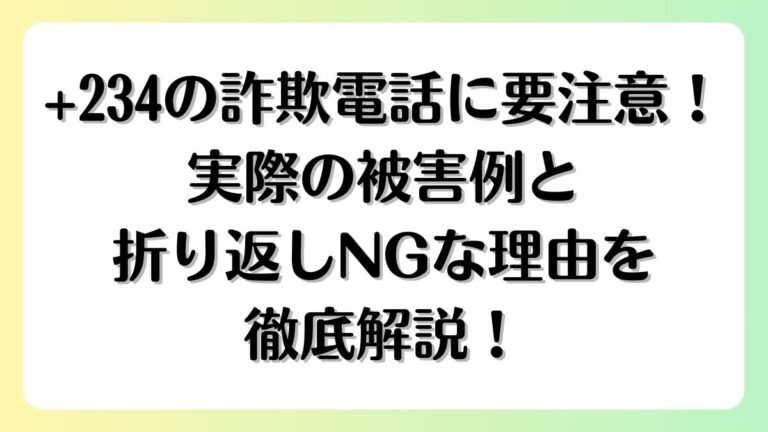最近「+234」からの謎の着信が増えていませんか?
それ、もしかしたら詐欺電話かもしれません。
この記事では、「+234 詐欺電話」の正体や危険性、実際の被害事例、そして着信があったときの正しい対処法まで、徹底的にわかりやすく解説します。
スマホの設定や便利な対策アプリ、そして被害に遭ってしまった場合の相談先まで紹介しているので、この記事を読めば安心できますよ。
知らない国番号からの着信に不安を感じた方は、ぜひ最後までチェックしてくださいね。
+234 詐欺電話は本当に危険なのか?実態と注意点

+234 詐欺電話は本当に危険なのか?実態と注意点について解説します。
それでは順番に見ていきましょう!
+234はどこの国の番号か
+234という番号は、アフリカの「ナイジェリア」の国番号です。
国際電話で「+234」から始まっているということは、ナイジェリアからかかってきているということになります。
ただし、実際にはナイジェリア国内からの発信ではなく、IP電話や偽装番号で世界中から発信されていることも多く、発信元の特定は非常に難しいのが現状です。
この番号を見て「何これ?」と思って調べた方は、とても正しい反応です。
「知らない海外番号=注意が必要」という意識を持っておくことが、被害の抑止につながりますよ!
なぜ日本にかかってくるのか
「ナイジェリアなんて知り合いもいないし…なんで?」と思いますよね。
実はこの手の詐欺電話、完全にランダムにかけてきているケースがほとんどなんです。
特にSMSや通話でのワン切りなど、リアクションを引き出すことが目的です。
日本の電話番号はインターネット上で漏洩していたり、懸賞や登録フォームなどから流出していることもあります。
海外の詐欺業者は、自動発信ツールを使って世界中に一斉に電話をかけているので、日本にかかってきても不思議ではありません。
「自分が狙われている」ではなく「誰でもかかってくるもの」と捉えて冷静に対応しましょう。
詐欺電話の目的と手口
一番多いのが「ワン切り詐欺」です。
一瞬だけ着信を残して、相手が気になって折り返してくるのを狙っています。
この折り返しがポイントで、国際電話の高額な通話料が発生し、詐欺業者に通話料の一部が流れる仕組みです。
他にも、英語や片言の日本語で「口座情報が必要」「荷物を受け取ってください」などと不安をあおる内容もあります。
「相手を焦らせて操作させる」のが手口の共通点ですので、まずは落ち着いて対応するのが鉄則です!
実際の被害事例
ネット上でも「+234からの電話に折り返してしまった」「3分通話しただけで3,000円請求が来た」などの報告が多数あります。
特に格安SIMや海外通話に対応しているプランでは、請求の仕組みが分かりにくく、後から高額請求に気づくケースもあります。
さらに「SMSに返信しただけでも通話と同じ扱いになることがある」といった情報も。
知らないうちに被害を受けていたということもあるので、少しでも怪しいと感じたら、履歴やSMSは保存しておきましょう。
そして請求内容をしっかり確認するクセをつけておくと安心ですよ!
無視していいのか折り返していいのか
結論から言うと、「絶対に折り返ししないこと」が最善です。
気になる気持ちは分かりますが、折り返すことで相手に「反応してくれた」と知られてしまい、さらに詐欺の対象としてマークされるリスクが高まります。
また、一度通話してしまうと高額請求の可能性もありますし、内容次第では個人情報を引き出されてしまうことも。
どうしても気になる場合は、逆電話検索サービスを使って情報を調べるにとどめて、絶対に直接通話はしないようにしましょう。
「無視する勇気」が、何よりの防衛手段です!
+234 詐欺電話を受けたときの正しい対処法5選

+234 詐欺電話を受けたときの正しい対処法5選についてご紹介します。
では、各対処法について詳しく見ていきましょう!
①絶対に折り返さない
+234から着信があったとき、まず最初にやってほしいことは「無視」です。
つい好奇心で「誰だろう?」と折り返したくなるかもしれませんが、それは相手の思うツボ。
このような詐欺電話の多くは、折り返しをさせて高額通話料を請求することを目的としています。
一度でも反応すると、リストに「応答する人」としてマークされ、さらに多くの詐欺電話を受けるリスクが高まるんです。
知らない番号、特に国際番号からの着信には、一切応答しないことが鉄則ですよ!
②着信拒否・ブロック設定をする
一度かかってきた番号は、今後も繰り返しかかってくる可能性が高いです。
そこで活用したいのが、スマートフォンの「着信拒否」機能や、通信会社が提供するブロックサービス。
iPhoneの場合は、着信履歴から該当番号をタップし、「この発信者を着信拒否」に設定できます。
Androidも同様に、通話履歴から設定が可能です。
また、各キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)や格安SIMでも「迷惑電話ストップサービス」などが提供されていますので、契約中のサービスをチェックしてみてくださいね!
③通話履歴・SMSの内容を保存しておく
万が一、電話を取ってしまった場合や、SMSが届いた場合には「記録を残す」ことが大切です。
具体的には、以下の情報をスクリーンショットやメモで保存しておきましょう:
| 記録しておくべき内容 | 理由 |
|---|---|
| 電話番号(+234〜) | 発信元の特定と通報時に必要 |
| 着信日時 | 時系列での整理や証拠提出に有効 |
| 通話の有無・内容 | 万が一課金された際の証明になる |
| SMSの本文 | 脅しや誘導メッセージの証拠 |
何かあったときに備えて、念のために残しておくことが自衛になります。
④不安な場合は警察や専門機関に相談
「これって詐欺かも…?」と思ったら、一人で悩まず相談することが大切です。
警察の「サイバー犯罪相談窓口」や、消費者庁の「消費者ホットライン(188)」が頼れる存在です。
こうした相談窓口では、過去の事例や被害状況に基づいて適切なアドバイスをしてくれます。
また、警察に相談することで、他の被害者の情報と照合されて、詐欺グループの摘発につながることもあるんです。
「このくらいで相談してもいいのかな?」なんて遠慮せず、少しでも不安があるなら連絡してみてくださいね。
⑤高額通話料金の仕組みを知っておく
なぜ詐欺電話に出ると高額な料金がかかるのか、不思議ですよね。
それは「国際電話の仕組み」と「通話料の分配構造」に理由があります。
簡単に言うと、折り返し通話がナイジェリアの電話事業者を通して接続され、その通話料の一部が詐欺業者にキックバックされる構造になっているんです。
特に、国際ローミングが有効になっている状態や、IP電話を使っている場合など、思わぬ高額請求が来るケースがあります。
利用中の携帯キャリアで「海外通話のブロック設定」や「明細の確認」などを見直すと、被害の防止に役立ちますよ!
+234 詐欺電話の被害を防ぐ設定とおすすめアプリ

+234 詐欺電話の被害を防ぐ設定とおすすめアプリについて解説します。
スマホやアプリを上手に活用すれば、詐欺電話の多くを事前に防ぐことができますよ!
スマホでの着信ブロック設定方法(iPhone/Android)
まずは、スマートフォン自体に備わっている「着信拒否機能」を活用しましょう。
iPhoneの場合は、以下の手順で設定できます:
- 「電話」アプリを開く
- 着信履歴から該当の番号をタップ
- 「この発信者を着信拒否」を選択
Androidスマホでも、機種によって若干異なりますが、基本は「通話履歴 → 番号の詳細 → 着信拒否に追加」で設定できます。
一度設定しておくと、同じ番号からの着信は鳴らずにスルーできるので、精神的にもラクになりますよ。
詐欺電話が来たあとすぐに対応するのがコツです!
迷惑電話対策アプリの紹介
次にご紹介したいのは、「迷惑電話対策アプリ」の活用です。
代表的なアプリは以下の通りです:
| アプリ名 | 主な特徴 | 対応OS |
|---|---|---|
| Whoscall | 着信相手の情報をリアルタイムで表示、迷惑電話の自動識別 | iOS/Android |
| 迷惑電話ブロック(NTTレゾナント) | 国内外の迷惑番号データベースに基づいて自動ブロック | Android |
| Truecaller | 世界中で使われている大規模な電話番号識別サービス | iOS/Android |
これらのアプリは基本的に無料で使えますが、一部の高機能には有料プランが必要なこともあります。
特に「着信前に危険な番号か判断できる」のがありがたいポイントですね!
通信会社のサービスを利用する
実は、携帯キャリア各社も迷惑電話対策に力を入れています。
以下に代表的なサービスをまとめました:
| キャリア | サービス名 | 特徴 |
|---|---|---|
| NTTドコモ | あんしんセキュリティ | 迷惑電話・詐欺SMSの自動警告とブロック |
| au | 迷惑メッセージ・電話ブロック | 専用アプリで詐欺SMSや迷惑電話を判定 |
| ソフトバンク | 迷惑電話ブロック | 危険な番号を自動で警告・遮断 |
多くのサービスが月額100〜300円ほどの有料ですが、「自分で番号を調べる手間がない」「見落とし防止になる」などのメリットは大きいです。
スマホ設定が苦手な方や、ご高齢のご家族におすすめですよ!
着信フィルターの活用法
最後に、迷惑電話がかかってくる前に自動で振り分ける「着信フィルター」の活用法です。
これはアプリやキャリアサービスの一部に含まれており、「海外からの着信をすべて通知しない」や「データベースで迷惑番号と一致したら通知しない」などの設定ができます。
たとえば、WhoscallやTruecallerなどは自動的に「スパムマーク」を表示してくれるので、受話前に判断できます。
また、フィルターが「音を鳴らさずに着信ログに記録」するモードを活用すれば、知らない番号の確認だけも可能です。
通知されなければ精神的な負担も減りますし、スマホ初心者でも設定しやすいのがうれしいポイントですね!
+234からの国際電話詐欺の仕組みをわかりやすく解説
+234からの国際電話詐欺の仕組みをわかりやすく解説します。
一見単純に見える詐欺電話ですが、実はかなり巧妙な仕組みが裏にあります。順番に見ていきましょう。
ワン切り詐欺のビジネスモデル
ワン切り詐欺は、基本的に「折り返させて高額な通話料を発生させる」ことが目的です。
まず、+234のような国際番号で1回だけ電話をかけてきて、着信履歴に残します。
このとき相手はすぐに切るので、電話に出ても何も話しませんし、SMSだけ送ってくることもあります。
気になった人が折り返すと、国際電話の通話料が発生し、その通話料の一部が、詐欺業者や関連の通信事業者にキックバックされる仕組みです。
つまり、「電話に出てもらう必要はない」「とにかく折り返してくれさえすれば利益になる」という、非常に効率的かつ悪質なモデルなんですね。
折り返すとどうなるのか
では、もしも折り返してしまったらどうなるのでしょうか?
まず、通話がつながっても、相手は意味のないことを話したり、無言だったり、録音された音声が流れるだけのこともあります。
その間にも、国際通話料は1秒ごとに課金されていきます。
1分100円〜数百円程度の通話料が発生するケースが多く、例えば2〜3分話しただけでも1,000円を超えることがあります。
しかも、それが1件では済まず、何度も電話がかかってきたり、別の番号から連絡が来たりすることで、被害が拡大してしまうこともあるんです。
こうした詐欺グループは、反応した人を「カモ」として名簿化し、さらに売買していることもあると言われています。
どこに課金されるのか
国際電話で課金される仕組みは、少し複雑です。
一般的には、通話料の一部が以下のように分配されます:
| 通話料の行き先 | 役割 |
|---|---|
| 日本の通信キャリア | 発信元として基本料金を徴収 |
| 国際通信会社 | 中継・接続のための費用 |
| ナイジェリアの通信会社 | 着信先として課金を受ける |
| 詐欺業者 | 着信通話の一部をキックバックとして受け取る |
このように、詐欺電話を利用して「通信費ビジネス」を展開している業者も存在するのが現実です。
あなたが折り返したその1分間が、複数の事業者にとっての収益源になっているというわけです。
なぜナイジェリアが多いのか
「なんでナイジェリアからばかりかかってくるの?」と思った方も多いと思います。
実は、ナイジェリアは以前から「ナイジェリア詐欺(ナイジリアン・スキャム)」と呼ばれる詐欺の温床として知られてきました。
偽のビジネス話や遺産相続詐欺なども多く、世界中の国々で警戒されている存在です。
詐欺集団が組織的に存在しているだけでなく、一部の通信インフラや金融システムの緩さも影響して、詐欺電話が発信されやすい環境となっているのです。
つまり、ナイジェリアが「たまたま多い」のではなく、「詐欺にとって都合がいい環境が揃っている」からなんですね。
もちろん、すべてのナイジェリア人が悪いわけではありませんが、「+234からの電話=警戒が必要」という意識はしっかり持っておきましょう。
被害に遭ったらどうする?+234 詐欺電話の相談窓口と対応策

被害に遭ったらどうする?+234 詐欺電話の相談窓口と対応策について解説します。
被害に遭ってしまったら、一人で悩まずに行動することが何より大切です。
消費者センターに相談
まず相談先としておすすめなのが「消費者ホットライン(188)」です。
この番号に電話をかけると、最寄りの消費生活センターにつながり、専門の相談員が対応してくれます。
特に、詐欺かどうか判断に迷ったときや、請求額が不明な場合などに、冷静なアドバイスをもらえます。
通話料は無料で、平日だけでなく土日も対応している地域が多いので、気軽に相談してみましょう。
「たった1回の電話」で、精神的にすごく安心できることも多いんですよ!
警察への相談方法
金銭的な被害が明らかだったり、明確な脅迫・詐欺の痕跡がある場合は、警察への相談も必要です。
サイバー犯罪相談窓口や最寄りの交番・警察署に連絡し、着信履歴やSMS、請求書などの証拠を提示しましょう。
都道府県警察のホームページから「サイバー犯罪相談窓口」が案内されているので、お住まいの地域に応じてアクセスしてみてください。
また、国際的な詐欺の場合、警察庁や外務省からの情報提供も重要になります。
相談したことで捜査が進み、他の被害者を救うことにもつながるかもしれません。
携帯会社への相談
スマホで国際電話に折り返してしまった場合、すぐに携帯会社にも相談を入れましょう。
各キャリアは、通話明細の確認や料金の再調整、ブロック対応など、さまざまな支援をしてくれます。
特に、まだ請求が確定していないタイミングであれば、事前に相談しておくことでトラブル回避につながることがあります。
| キャリア名 | 相談窓口 | 対応内容 |
|---|---|---|
| ドコモ | 151(無料) | 国際通話の明細・設定確認、料金相談 |
| au | 157(無料) | 詐欺被害に関する相談・履歴確認 |
| ソフトバンク | 157(無料) | 通話停止や再発防止策の案内 |
困ったらすぐ連絡、が鉄則です。泣き寝入りせず、動きましょう!
今後の再発防止の心得
一度被害に遭ったからこそ、今後に備える意識が大切です。
再発防止のポイントとしては、以下のようなことが挙げられます:
- 国際電話の着信はすべて拒否に設定する
- 迷惑電話ブロックアプリを導入する
- 電話番号を安易に他人に教えない・ネットに登録しない
- 家族や周囲の人とも情報を共有する
特に高齢のご家族がいる場合、「知らない海外番号は絶対出ないように」と共有しておくと安心です。
詐欺は防ぐより、引っかかってからの方がダメージが大きいので、「仕組みを知っておく」「対策をしておく」ことが何よりの武器になりますよ!
実は多い!+234以外にも要注意な国番号一覧

実は多い!+234以外にも要注意な国番号一覧を紹介します。
+234だけじゃなく、他にも危ない国番号は実はたくさんあります。
見覚えのない番号には特に注意してくださいね。
+255(タンザニア)
+255は東アフリカにある国「タンザニア」の国番号です。
最近、日本でも「+255」からのワン切り詐欺が急増していると報告されています。
ナイジェリア同様、折り返しを狙う手口で、通話料ビジネスにつなげる構造はほぼ同じです。
SMSが一緒に届くこともあり、「再配達の確認」「銀行アラート」など、よくある偽メッセージで誘導されるパターンもあります。
+255の番号が残っていたら、すぐにブロックしておきましょう!
+44(イギリス)を装う手口
+44はイギリスの国番号で、ビジネスでもよく使われる番号なので、油断しがちです。
ところがこの+44も、詐欺に使われることがあります。
「大手企業を装った連絡」や「Amazon UKからの重要連絡」などを名乗ることがあり、本物に見せかけてクリックや通話を誘導する手口です。
特に日本語が混ざったSMSや、知っている会社名を語る場合は要注意!
本当に該当する取引があったかどうかを、まず公式サイトやアプリから確認してみてくださいね。
+81(日本)でも偽装詐欺に注意
なんと、日本の国番号「+81」ですら、詐欺に悪用されていることがあります。
これは「番号偽装」と呼ばれ、本当は海外からの発信なのに、見た目だけ+81に偽装してくるんです。
詐欺グループが専用のツールを使って、日本国内の番号に見せかけることで、警戒心を和らげようとします。
一見普通の番号でも、「知らない番号」「不自然なタイミングの着信」には注意してください。
特に、留守電にメッセージが残っていない、何も話さない場合は怪しいサインです!
国番号の見分け方と検索方法
最後に、怪しい電話番号がかかってきたときに役立つ「国番号の見分け方」について紹介します。
国番号とは、「+」に続く1〜4桁の数字で、その番号から発信国がわかります。
例えば:
| 国名 | 国番号 |
|---|---|
| 日本 | +81 |
| ナイジェリア | +234 |
| タンザニア | +255 |
| イギリス | +44 |
知らない番号が来たら、まずは「国番号 国名」で検索するだけでも発信元が確認できます。
さらに、逆引き電話番号検索サイト(例:tellows、Whoscallなど)を活用することで、過去の通報情報などもチェック可能です。
「すぐに反応しない」「まず調べる」という習慣を身につけておけば、トラブルはかなり回避できますよ!
まとめ|+234 詐欺電話は即ブロックが鉄則
| +234 詐欺電話の注意点まとめ |
|---|
| +234はどこの国の番号か |
| なぜ日本にかかってくるのか |
| 詐欺電話の目的と手口 |
| 実際の被害事例 |
| 無視していいのか折り返していいのか |
+234からの着信があったら、それは詐欺電話の可能性が非常に高いです。
ナイジェリアを発信元とするワン切り詐欺や高額通話料詐欺は、今や誰でも被害に遭う可能性があります。
不審な番号からの着信には出ない、折り返さない、ブロック設定や対策アプリを活用する。
この3つの基本を押さえることで、被害を未然に防ぐことができます。
もしも通話してしまったり、SMSに反応してしまった場合でも、慌てずに証拠を残し、警察・消費者センター・携帯会社へすぐ相談しましょう。
安心してスマホを使い続けるために、「知らない番号には出ない」という習慣を今日から身につけておくことを強くおすすめします。
参考リンク:
・消費者庁|迷惑電話やSMSにご注意ください
・警察庁|サイバー犯罪対策