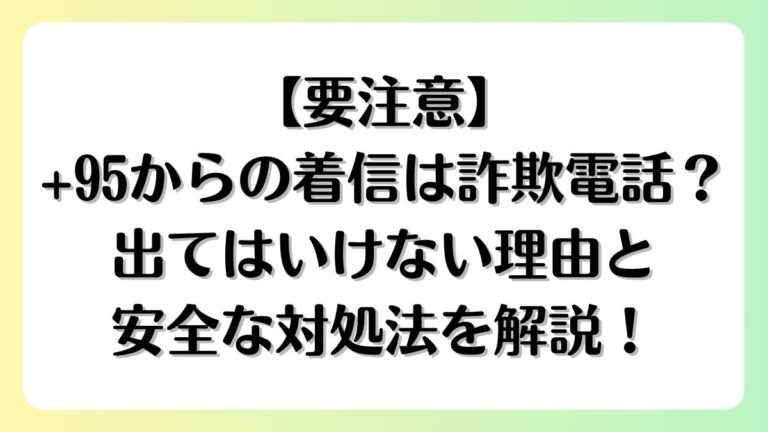突然の「+95」からの着信、出ていいのか不安になったことはありませんか?
+95はミャンマーの国番号で、実は詐欺電話の温床とも言われているんです。
本記事では、「+95詐欺電話」の危険性や具体的な手口、そして被害を防ぐための対処法まで、徹底的にわかりやすく解説しています。
この記事を読めば、怪しい電話にどう対応すべきかが明確になり、自分や家族を守る行動が取れるようになりますよ。
ぜひ最後までチェックして、安全対策に役立ててくださいね。
+95詐欺電話が危険な理由と対処法
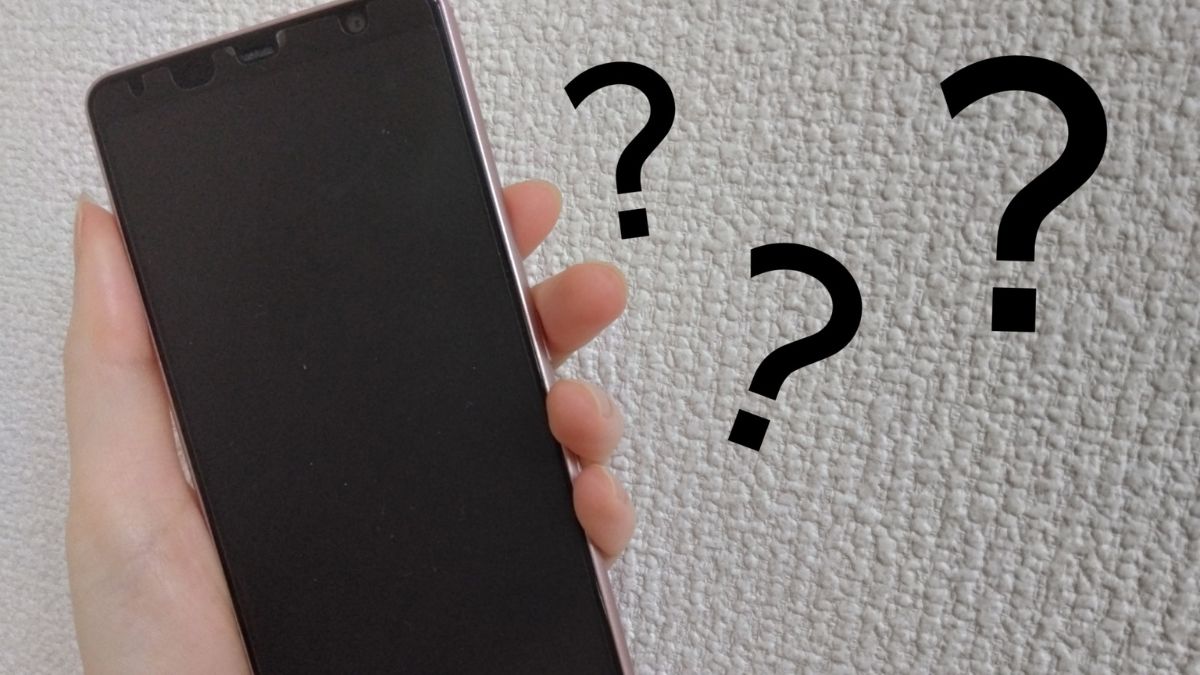
+95詐欺電話が危険な理由と、その対処法について解説します。
それでは、詳しく見ていきましょう。
+95はミャンマーの国番号
「+95」はミャンマーの国番号です。
つまり、+95から始まる電話番号は、基本的にミャンマーからかかってきているということになります。
もちろん、正規のビジネスや知人からの電話もあるかもしれませんが、日本に住んでいてミャンマーに知り合いがいない場合、突然の着信には注意が必要です。
最近では、この「+95」の番号を使った詐欺電話が急増しており、SNSなどでも「+95からの着信があったけど出ていいの?」という不安の声が多く聞かれます。
正体不明の海外番号からの着信は、基本的に警戒しておくのが無難です。
詐欺業者が国際電話を悪用している
詐欺グループは、国際電話という仕組みを悪用して、巧妙な手口で個人情報やお金を狙ってきます。
例えば、非通知や国際番号を使ってかけることで、受信者に「これは大事な電話かも」と思わせたり、「折り返しが必要かな」と思わせたりする心理を突いてきます。
特に、+95のような普段見慣れない国番号は、かえって不安をあおり、行動を起こさせる材料にされがちです。
また、最近では自動音声を使って「重要な手続きがあります」や「警察からの連絡です」といった言葉で脅してくるケースもあります。
少しでも不審に思ったら、まずは出ない・調べることが大切ですよ。
電話に出ると被害につながるケースも
実際に電話に出てしまった場合、どんな被害があるのでしょうか?
まず、相手に自分が電話を使っていることがバレるため、「この番号は使われている」と判断され、詐欺リストに追加されることがあります。
また、自動音声やオペレーターが個人情報を聞き出そうとしたり、ボタン操作を促してきたりすることもあります。
これに応じてしまうと、名前や住所、銀行口座の情報を盗まれる可能性が出てきます。
さらに、操作の内容によっては、悪質なサービスへ登録されてしまうリスクもあるんです。
ですので、見知らぬ+95の番号から着信があっても、絶対に出ないことが第一の防衛策です。
折り返し電話で高額請求されることがある
「誰だろう?」と気になって、つい折り返し電話をしてしまう人もいると思います。
しかし、これはもっとも危険な行動の一つです。
というのも、詐欺電話のなかには、いわゆる「ワンギリ詐欺」のように、受信者に折り返させることで高額な通話料を発生させる仕組みを取っているものがあります。
国際電話の通話料金は非常に高く、数十秒〜数分でも数千円以上の請求が来ることも。
さらに、相手がプレミアム回線(高額課金される電話回線)を使っていた場合、その請求額はさらに跳ね上がります。
着信履歴に+95があっても、無視する勇気が自分を守る第一歩です。
次の章では、詐欺電話の手口についてさらに掘り下げていきます。
詐欺電話の具体的な手口5パターン

詐欺電話の具体的な手口5パターンについて詳しく解説します。
どれも非常に巧妙なので、ひとつずつ対策とともに見ていきましょう!
①自動音声での不審な案内
最近増えているのが、自動音声を使った詐欺電話です。
電話に出ると、「こちらは●●銀行です。口座に異常がありました」や「警察からの連絡です。重要なお知らせがあります」などと機械音声で話しかけてきます。
このタイプの詐欺は、人間の声ではなく機械の声を使うことで、「なんとなく本物っぽい」と感じさせるのがポイント。
「1を押してください」「担当者におつなぎします」などとボタン操作を求めることが多いですが、絶対に応じてはいけません。
押した時点で個人情報を盗られたり、有料サービスに誘導される可能性がありますからね。
②偽のアンケート電話
「簡単なアンケートにご協力ください」といった内容でかかってくる電話も要注意。
一見すると無害そうですが、「お住まいの地域は?」「年収帯は?」「持ち家ですか?」など、個人情報を聞き出す内容になっていることがほとんどです。
その情報がリスト化され、後日さらに悪質な詐欺へ利用されるケースもあるんです。
特に、「豪華景品が当たるチャンスです」といった甘い言葉には気をつけましょう。
筆者の知人もこの手口に引っかかって、後日なぜか高額商品の勧誘電話が殺到するようになってしまいました…。
③有料サービスの偽装登録
「あなたの端末で有料サービスへの登録が確認されました」といった詐欺電話もあります。
これは「知らない間に何か登録してしまったのでは?」という不安を煽る手口です。
さらに「今すぐキャンセル手続きをしないと、課金が続きます」と急がせてきます。
ここで案内された電話番号にかけたり、URLをクリックしてしまうと、詐欺サイトに誘導されて個人情報を抜かれてしまいます。
本当に登録した覚えがないのなら、まずはそのまま無視してOKです。信頼できるサポート窓口に確認するのが正しい対応ですよ。
④荷物の再配達を装う手口
「お荷物の再配達について確認が取れていません」という内容で、SMSや電話が来るパターンも詐欺のひとつです。
この手口は特に年末年始やセール時期など、荷物が届くタイミングを狙って多発します。
本物の宅配業者を名乗ることもあり、「ヤマト運輸」「佐川急便」といった大手の名前が使われることもあります。
SMS内に記載されたリンクをタップしてしまうと、偽サイトに誘導されてしまい、そこから個人情報やクレジットカード情報が盗まれてしまう危険があります。
荷物の確認は、公式アプリや公式サイトを通じて行うのが安全ですよ~!
⑤警察や金融機関を名乗る詐欺
最後に紹介するのは、かなり悪質な「警察官」「金融機関の職員」を名乗る詐欺です。
「あなたの口座が犯罪に使われている可能性がある」などと脅してきて、口座番号や暗証番号を聞き出そうとします。
また、「キャッシュカードを安全な場所に保管するため、職員が受け取りに行きます」と言って、直接取りに来るケースもあります。
これは、いわゆる「預貯金詐欺」の典型的な手口で、高齢者を狙った被害が後を絶ちません。
本物の警察や金融機関が、電話で個人情報を聞き出したり、カードを取りに来ることは絶対にありませんので、絶対に信用しないでくださいね!
ここまでが主な手口の紹介でした。次の章では、もし詐欺電話を受けたときの具体的な対応方法を紹介していきます!
+95詐欺電話を受けたときの対応マニュアル

+95詐欺電話を受けたときの対応マニュアルをまとめます。
いざというとき慌てないためにも、対応策をしっかり頭に入れておきましょう!
電話に出ない・折り返さない
まず基本中の基本ですが、見知らぬ+95番号からの電話には「出ない・折り返さない」ことが最も重要です。
詐欺電話は、出てしまった時点で「この番号は生きている」と判断され、さらなる詐欺の対象になる可能性があります。
また、折り返してしまうと国際通話料金が発生し、思わぬ高額請求を受けるおそれもあります。
とくに、ワンギリのような手口で折り返しを誘導する場合もあるため、何度もかかってくるからといって反応してはいけません。
心配な場合は、まずネットで番号を検索してから判断しましょうね。
着信拒否設定を活用する
iPhoneやAndroidなど、多くのスマホには着信拒否機能がついています。
一度でも怪しいと思った番号は、すぐに「着信拒否リスト」に登録しておくと安心です。
特にiPhoneでは「連絡先に登録していない番号をサイレント着信にする」機能もありますので、活用するとよいでしょう。
また、キャリア(ドコモ、au、ソフトバンクなど)によっては、迷惑電話対策サービスを提供しているので、併用することでさらに安心度が高まりますよ。
設定方法は各機種で異なりますが、検索すればすぐに出てくるので、ぜひ試してみてください。
不審な番号を検索する
「この番号、怪しいけどどうしよう…」と思ったら、まずはインターネットで検索してみてください。
最近では、電話番号ごとの口コミ情報を集めたサイト(「電話帳ナビ」や「jpnumber」など)が充実しています。
そこに「詐欺だった」「無言電話」「ワン切りされた」などの投稿があれば、その番号は危険と判断できます。
リアルタイムに被害情報が更新されていることも多く、特に詐欺が流行している時期には有効です。
不審な番号はすぐ調べて、自分でも情報共有すると、他の人の被害も防げるのでおすすめです!
通話記録を保管しておく
万が一、詐欺被害につながってしまった場合に備えて、通話履歴や録音などを残しておくのも重要です。
スマホには通話履歴が残りますし、一部の機種では自動録音機能も使えます。
不審な会話内容や相手の声、勧誘内容などは、被害の証拠として大きな意味を持ちます。
後から「何を言われたか思い出せない」という状況にならないよう、記録を習慣化しておくと安心ですよ。
記録しておけば、警察や消費者センターに相談する際にも話がスムーズになります。
消費者センターや警察に相談する
実際に被害に遭った、もしくは未遂でも不安がある場合は、ためらわずに相談機関を活用してください。
まずおすすめなのは「消費者ホットライン(188)」です。局番なしでかけると、最寄りの消費生活センターにつながります。
また、被害が金銭に関わる場合や悪質な場合は、すぐに警察(最寄りの警察署または#9110)へ連絡を。
被害届けを出すことで、同様の手口の捜査に役立ち、他の被害者を守ることにもつながります。
泣き寝入りせず、しっかりと行動を起こしましょうね。
ここまで対応マニュアルをお届けしましたが、次の章ではそもそも被害を未然に防ぐための方法をご紹介します!
被害を防ぐために今すぐできる5つのこと
 被害を防ぐために今すぐできる5つのことをお伝えします。
被害を防ぐために今すぐできる5つのことをお伝えします。
未然に防げることも多いので、今すぐ実践してみてくださいね!
①スマホのセキュリティ設定を見直す
まず、スマホのセキュリティ設定を今一度見直してみましょう。
例えば、「提供元不明のアプリのインストールを許可している」設定になっていると、偽アプリを入れられるリスクが高まります。
iPhoneでは「プライバシー設定」や「通話のブロックと着信拒否」を、Androidでは「セキュリティ」や「通話設定」を見直すのがおすすめです。
自分のスマホを安全に保つためには、設定の確認とアップデートを怠らないことがポイントです。
もし不安な場合は、携帯ショップで設定サポートを受けるのもアリですよ〜。
②国際電話の発信を制限する
知らないうちに国際電話を発信してしまうリスクを減らすには、キャリア側で「国際電話の発信制限」を設定しておくのが安心です。
各通信キャリア(ドコモ、au、ソフトバンクなど)では、オプションで発信制限が設定できます。
特に、子どもや高齢者のスマホは、間違ってかけてしまう可能性があるので、あらかじめ制限しておくとトラブル防止につながります。
設定方法はキャリアごとに違いますが、「マイページ」や「サポート」にアクセスすれば簡単に手続きできますよ。
不安な方は、サポートセンターに直接問い合わせるのが確実です!
③迷惑電話対策アプリを入れる
最近では、迷惑電話を自動でブロックしてくれるアプリがたくさん登場しています。
たとえば「Whoscall(フーズコール)」や「迷惑電話ストップ」などが有名ですね。
これらのアプリは、過去の通話データベースやユーザーの報告情報をもとに、着信時に「詐欺の可能性あり」と警告してくれます。
さらに、一部アプリでは自動でブロックする機能や、発信者の情報を表示してくれる機能もあります。
無料版でも十分に使えるものが多いので、インストールしておいて損はありませんよ。
④高齢の家族にも注意を呼びかける
高齢者の方は、詐欺電話のターゲットになりやすい層です。
「知らない番号でも、失礼があってはいけないと思って出てしまう」という心理が働きやすいため、特に注意が必要です。
一緒に住んでいる方がいれば、定期的に「こういう電話には絶対出ないで」と声をかけてあげてください。
離れて暮らしている場合でも、LINEや電話で連絡を取って、注意喚起するだけでも大きな効果があります。
筆者も実家の親に「+95は詐欺電話かも」と伝えたことで、危うく被害を防げたことがありましたよ〜!
⑤情報をSNSなどで共有する
最後に、ぜひやっていただきたいのが「情報のシェア」です。
Twitter(X)やInstagram、Facebookなどで、「+95から電話きた!調べたら詐欺だった」などと発信することで、他の人にも警告を伝えることができます。
また、電話番号の口コミ投稿サイトに書き込むことで、さらに多くの人に注意を促せます。
ネットの力は強力で、リアルタイムで詐欺の情報が広まり、被害の抑止につながります。
ちょっとした投稿でも、誰かを救うきっかけになりますので、ぜひ協力してくださいね!
ここまでで、具体的な予防策をお伝えしました。次は、+95以外にも注意すべき国番号を一覧でご紹介します。
+95以外にも注意すべき国番号一覧

+95以外にも注意すべき国番号を一覧で紹介します。
「+95=詐欺電話」と思われがちですが、実は他の国番号からも怪しい電話がかかってくるケースは増えています。
+94(スリランカ)
+94はスリランカの国番号です。
日本との交流が比較的少ない国でもあるため、+94からの突然の着信はまず不審を抱いてOKです。
SNSなどでも「+94から何度もかかってくる」「出たら無言だった」といった報告が見られます。
通話に出たことで詐欺リストに載ってしまう危険もあるため、スルーして調べるようにしましょう。
着信拒否の対象としても早めに登録しておきたい番号です。
+880(バングラデシュ)
バングラデシュの国番号である+880も、注意が必要な番号のひとつです。
詐欺業者の一部が、この番号を使って日本のスマホに大量発信しているという情報があります。
筆者が確認した事例では、「外国語で一方的に話された」「すぐ切れた」といった被害報告がありました。
日本語で話されないからといって無害とは限りません。
一瞬で高額な国際料金が発生する可能性もあるので、要注意です。
+84(ベトナム)
ベトナムの国番号である+84は、日本との関係が深いため、少しだけ判断が難しい番号でもあります。
技能実習生や現地法人とのやり取りがある人にとっては、正規の連絡先であることもあります。
ただし、その信頼感を逆手に取って詐欺に使われているケースもあるんです。
たとえば、「国際交流団体」を名乗って連絡し、口座情報を聞き出すなどの報告がありました。
心当たりがない場合は、やはり出ずに調べることがベストです。
+993(トルクメニスタン)
+993はトルクメニスタンの国番号ですが、日本とはあまり接点のない国です。
そのため、+993から電話がかかってきた場合は、かなり高い確率で詐欺の可能性が考えられます。
特に、「1コールで切れる」「折り返すと外国語の自動音声が流れる」といった典型的なワンギリ詐欺の手口が報告されています。
このようなケースでは、絶対に折り返さないようにしましょう。
通話料目的の詐欺である可能性が高いです。
+686(キリバス)
キリバスという国をご存じない方も多いかもしれませんが、+686はその国番号です。
南太平洋にある小さな国で、日本とは直接的なつながりはほぼありません。
このようなマイナーな国番号が表示されたら、それだけで警戒信号と考えて良いでしょう。
実際に、+686からの着信による迷惑行為の報告もあり、折り返し通話による高額請求の被害も確認されています。
どこの国か分からない番号には、なおさら慎重になってくださいね。
このように、+95だけでなく、他の国番号からも不審な電話がかかってくることがあるので、警戒心を常に持っておきましょう。
まとめ|+95詐欺電話に出ない・調べる・相談する
| +95詐欺電話が危険な理由 |
|---|
| +95はミャンマーの国番号 |
| 詐欺業者が国際電話を悪用している |
| 電話に出ると被害につながるケースも |
| 折り返し電話で高額請求されることがある |
+95というミャンマーの国番号からかかってくる電話は、詐欺の可能性が非常に高いです。
知らずに電話に出てしまうと、「この番号は使われている」と認識されて、さらなる詐欺の対象になることもあります。
折り返してしまえば、高額な通話料を請求されるリスクすらあります。
こうした被害を防ぐには、まず「出ない」「調べる」「相談する」の3ステップが非常に有効です。
着信があっても無視し、番号をネットで検索して詐欺情報をチェックし、怪しいと感じたらすぐに消費者センターや警察に連絡しましょう。
さらに、スマホの設定で国際電話の制限をかけたり、迷惑電話ブロックアプリを活用したり、家族にも注意を促すことで、自分や大切な人の身を守ることができます。
+95だけでなく、他の不審な国番号にも警戒を広げることで、より安心・安全にスマホライフを送れますよ。
今回紹介した情報は、今後も変化していく可能性があります。
最新情報を常にチェックしつつ、被害に遭わないための意識を持ち続けてくださいね。
関連情報として、詐欺被害防止に役立つ公式サイトのリンクも載せておきます。