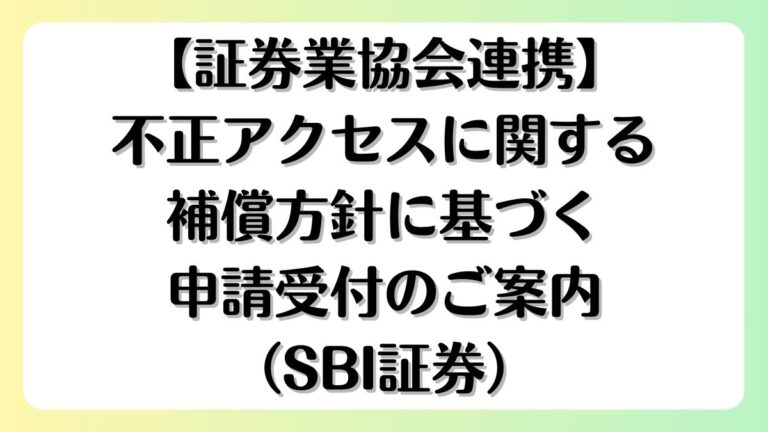「SBI証券から不正アクセスの補償申請メールが届いたけど、これって本物…?」
そんな不安を感じた方へ、この記事では実際に届いた詐欺メールの全文を公開し、その見分け方や対処法を徹底解説しています。
送信元のアドレスやリンクの罠、メールヘッダーの確認ポイントまで、具体的でわかりやすく解説。
さらに、もしうっかりクリックしてしまった場合の対応方法や、詐欺に引っかからないための予防策まで網羅しました。
この記事を読めば、今後同じようなメールが来ても、冷静に見抜いて行動できるようになりますよ。
ぜひ最後まで目を通して、自分と大切な人を守る知識を身につけてくださいね。
SBI証券を装った詐欺メールの全文と内容を解説

SBI証券を装った詐欺メールの全文と内容を解説します。
それでは詳しく見ていきましょう。
実際に届いた詐欺メールの全文
まずは実際に届いた詐欺メールの全文をご紹介します。
メールの件名は以下の通りでした:
【証券業協会連携】不正アクセスに関する補償方針に基づく申請受付のご案内(SBI証券)
一見すると、SBI証券からの正式なお知らせのように見えますよね。
本文は次のような内容でした:
【重要】不正アクセス補償申請のご案内(5月31日締切)
平素よりSBI証券をご利用いただき、誠にありがとうございます。2025年5月、日本証券業協会より、全国の証券口座におけるフィッシング詐欺・不正アクセス被害に関する補償方針が通達されました。
これに伴い、当社でも影響が懸念されるお客様への補償対応を開始しております。対象となるケースでは、外部からの不正ログインにより、口座内資産の操作または閲覧が行われた可能性があり、事前の申請が補償適用の前提条件となっております。
下記リンクより、お客様の状況をご確認いただき、必要に応じて補償申請手続きをお進めください。
補償申請期限:2025年5月31日(土)23:59
※上記期日を過ぎた場合、補償対象外となる可能性がございます。
■ 補償申請はこちら:
補償申請ページへアクセスする
申請には、お客様の登録情報および一部取引履歴等の照合が必要となる場合がございます。
あらかじめご準備をお願いいたします。※ すでにお手続きを完了されたお客様は、本ご案内への再対応は不要です。
本件に関するご不明点は、SBI証券カスタマーセンターまでお問い合わせください。
発行元:SBI証券株式会社
〒106-6019 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
Copyright © SBI SECURITIES Co., Ltd. All Rights Reserved.
文面自体はとても丁寧で、よく作り込まれています。
だからこそ「本物かも…?」と騙されてしまう方も多いんですよね。
では、このメールのどこに違和感があるのか、次で細かく見ていきましょう。
件名や本文の不審な表現に注目
件名にある「証券業協会連携」や「補償申請のご案内」といった表現は、いかにも公式っぽいですよね。
でも、実際には日本証券業協会が個別にメールで案内することはまずありません。
しかも「補償申請期限:◯月◯日」といった“急がせる”表現があるのも、詐欺メールの定番です。
不安を煽って冷静な判断を奪うやり口ですね。
焦らせてリンクをクリックさせるのが狙いです。
リンクの文言に潜む危険性
このメールの中で特に危険なのが、「補償申請ページへアクセスする」というリンクです。
一見すると正規のSBI証券のサイトに見えるかもしれませんが、実際には偽サイトに誘導されるケースがほとんどです。
リンク先のURLをよく見ると、sbi.co.jpではなく「ruwp.net」など、まったく関係のないドメインが使われていることがあります。
リンクを踏んだだけでマルウェアに感染したり、個人情報を盗まれる危険もあるんですよ。
見慣れないドメインが使われていたら、絶対にアクセスしないようにしてくださいね。
このあたりの見分け方についても、次の章でさらに詳しく解説していきます!
このメールが詐欺だと判別できる5つのポイント

このメールが詐欺だと判別できる5つのポイントを紹介します。
順番に見ていきましょう!
①送信元メールアドレスが公式ではない
一番最初に確認したいのが「From」欄のメールアドレスです。
今回のメールでは、Sbi.tozaki.kyouko@ruwp.net というアドレスから送られてきています。
一見「SBI証券の関係者かな?」と思わせるような名前ですが、公式ドメインの「sbisec.co.jp」ではありません。
このように、表示名だけ本物っぽくして、実際のドメインは全く無関係なものを使うのは、典型的な詐欺手口です。
公式企業のメールは、基本的にその企業のドメインで送られてきます。
まずここで「おかしいな」と疑ってくださいね。
②ドメインがSBI証券と無関係
「ruwp.net」というドメイン、あなたは見たことありますか?
多くの方にとっては聞き慣れないはずですし、SBI証券ともまったく無関係です。
これは詐欺グループが取得した怪しいドメインの可能性が高いですね。
こうした無関係なドメインは、リンク先の偽サイトでも使われがちです。
送信元とリンク先、両方のドメインを必ずチェックする癖をつけておきましょう。
③不自然な日本語表現
一見丁寧で正しい日本語に見えるメールですが、よく読むと少し引っかかる表現が混じっています。
例えば「補償方針が通達されました」「影響が懸念されるお客様」など、やや過剰で曖昧な表現が目立ちます。
本物の企業メールは、もっと明確で簡潔な文章が多いんですよね。
こういった「何となく不自然な丁寧さ」も、詐欺メールの特徴のひとつです。
違和感を感じたら、一度立ち止まって確認してみましょう。
④偽装されたHTMLリンク
HTMLメールの中には、リンクの表示名と実際の飛び先が違うケースがよくあります。
今回のメールでも「補償申請ページへアクセスする」と表示されていますが、リンク先は明記されていません。
こうしたリンクは、HTMLでタグを使って偽装されている可能性が高いです。
マウスをリンクの上に置くと、ブラウザの左下などに「実際のURL」が表示されるので、必ず確認してください。
「https://sbi.secure-login.jp」など、本物っぽく見せた偽URLが使われるケースもあります。
見た目だけで安心しないようにしましょう!
⑤メールヘッダーに不審なIPやリレー履歴
やや高度な方法にはなりますが、メールヘッダーの解析も有効です。
今回のメールでは、Receivedの情報を辿ると「189.107.215.105」というIPアドレスが使われており、これは南米地域にある個人サーバーの可能性があります。
さらに、途中で「vm283」「ebmky117sc」といった正規のSBIとは無関係なホスト名も登場しています。
こうした情報は、メールソフトの「ソースを表示」機能などで確認できます。
慣れてきたら、この方法も覚えておくと安心ですよ。
詐欺メールに騙されないための具体的な対策5選

詐欺メールに騙されないための具体的な対策5選を紹介します。
どれも簡単にできるので、ぜひ覚えておいてくださいね。
①メールアドレスとドメインを必ず確認する
まず最も基本的で効果的なのが、送信元のメールアドレスを確認することです。
表示名だけ見て「SBI証券」と書かれていても安心しないでください。
重要なのは「@」より右側のドメイン部分です。
公式なら「@sbisec.co.jp」「@sbi.co.jp」などになりますが、「@ruwp.net」など見慣れないものは明らかに偽物です。
パッと見では分からないように巧妙に作ってあることもあるので、細かくチェックする癖をつけましょう。
②正規サイトからログインして確認する
メールに書かれているリンクからアクセスするのではなく、Googleなどで公式サイトを検索して、自分でURLを入力してアクセスするのが安全です。
SBI証券の場合は「https://www.sbisec.co.jp」です。
気になるお知らせが来たときは、ログイン後の「お知らせ」欄や「メッセージボックス」を見れば、正しい情報が載っています。
メール内のリンクは信じず、必ず公式経由で確認しましょう。
これだけでも、詐欺のほとんどは防げますよ!
③クリックせずにURLをプレビュー確認する
リンクをクリックする前に、必ず「どこに飛ぶのか」を確認しましょう。
パソコンならリンクの上にマウスを置くと、左下やステータスバーにURLが表示されます。
スマホの場合はリンクを長押しすればプレビューが出ることもあります。
このとき、URLが「sbisec.co.jp」など公式ドメインでない場合は絶対にクリックしてはいけません。
少しの注意で、リンクの罠は簡単に見破れます。
④メールヘッダー情報をチェックする習慣をつける
メールの詳細情報(ヘッダー)を見ることで、そのメールが本当に正規の経路を通って届いたのか確認できます。
たとえば「Received」や「Return-Path」「From」などを見れば、IPアドレスやサーバー名が確認できます。
今回の詐欺メールでは、南米地域のIPや、SBI証券とは無関係なサーバーが使われていました。
慣れていないと少し難しく感じるかもしれませんが、慣れるとかなり有効な防御手段になります。
ビジネス用途でメールを使う人は、特に覚えておくと安心ですよ!
⑤疑わしい場合はカスタマーセンターへ直接確認
少しでも「怪しいな」「本当かな?」と思ったときは、メール内のリンクを使わずに、公式サイトからカスタマーセンターへ問い合わせましょう。
その場で判断せず、ひと呼吸置いて公式の連絡先を探すことが大切です。
「補償対象かも」「締め切りが近い」と焦らされても、冷静さが一番の防御になります。
SBI証券では、こういった詐欺に関する案内や注意喚起も公式サイトに掲載されています。
自分の判断に自信がないときほど、誰かに相談するのがいちばんですよ。
もしリンクをクリックしてしまったら取るべき行動

もしリンクをクリックしてしまったら取るべき行動を解説します。
被害を最小限に抑えるため、迅速な対応がカギです!
即座にネットワークを切断する
まず、リンクをクリックしてしまった直後に最初にすべきことは、Wi-Fiやモバイル通信をすぐにオフにすることです。
なぜなら、クリックと同時にウイルスやマルウェアがダウンロードされる恐れがあるからです。
ネットに繋がったままだと、個人情報が外部に送信されてしまう可能性も。
パソコンならLANケーブルを抜く、スマホなら機内モードにするなどして、まず「通信を遮断」しましょう。
それだけでも、かなりのリスクを減らせますよ。
パスワードの変更と口座確認を行う
次にすぐやってほしいのが、SBI証券をはじめ、関連するすべてのアカウントのパスワードを変更することです。
特に「いつも同じパスワードを使っている」という方は要注意。
もし偽サイトに入力してしまっていた場合、IDとパスワードは完全に盗まれています。
その状態で放置すると、別のサービスや銀行にも不正ログインされる可能性が高いです。
変更したあとは、ログイン履歴や取引履歴も確認しておきましょう。
セキュリティソフトでスキャン
リンクを開いただけで感染するタイプのマルウェアもあるので、セキュリティソフトでフルスキャンをかけておくと安心です。
市販のソフトを使っている人はもちろん、Windows Defenderなどの標準機能でもかまいません。
ウイルスが検出された場合は、駆除ツールを使って安全な状態に戻してください。
スマホの場合も、セキュリティアプリでのチェックを忘れずに。
感染をそのままにすると、後から被害が広がることもあるので早めに対応しましょう。
フィッシング被害相談窓口へ連絡
日本にはフィッシング詐欺に特化した相談窓口もあります。
たとえば、フィッシング対策協議会では、詐欺サイトの通報や相談が可能です。
被害に遭った可能性がある場合や、類似の詐欺を未然に防ぐためにも、通報はとても大切です。
企業も「報告件数」が多い詐欺には早く対応してくれます。
情報共有は、被害拡大を防ぐ第一歩です。
警察・消費者センターへの相談
実際に金銭被害が出てしまった場合や、個人情報を入力してしまったときは、警察や消費生活センターに連絡しましょう。
「サイバー犯罪相談窓口」や、国民生活センターも心強い相談先です。
放置してしまうと、被害が広がる恐れがありますし、何より自分を守るためにも動いてください。
「相談していいのかな?」と迷う場合でも、遠慮せず問い合わせてOKです!
詐欺メールは巧妙化!情報リテラシーを高めよう
詐欺メールは巧妙化しているため、情報リテラシーを高めることが必要です。
ここから先は、少しだけ先回りして対策を考えていきましょう。
実在企業を装った詐欺が増加
最近の詐欺メールの傾向として目立つのが、「実在する有名企業を装う手口」です。
たとえば今回のように「SBI証券」や「楽天」「Amazon」など、誰もが知っている大手企業の名前を使ってきます。
これによって、「本物かもしれない」と思わせて、信頼させるんですね。
実際に会社名だけで安心してリンクを開いたり、個人情報を入力してしまう人も多いです。
企業名を見ただけで判断せず、「本当にその企業が発信しているのか」を冷静に確認することが大事です。
AIによる文章の巧妙化
さらに最近では、生成AI(人工知能)を使って作られた詐欺メールも増えてきました。
以前は明らかに怪しい日本語が多かったのですが、今ではまるでプロが書いたような自然な文章も多いです。
語彙や敬語の使い方も精密で、見分けがつきにくくなってきています。
AIは人間の文体を模倣できるので、「文章が丁寧だから安心」とは限らないんです。
内容やリンク、ドメインまでしっかり見て判断するようにしましょうね。
SNSやSMSとの連携型詐欺も注意
詐欺の手口はメールだけにとどまりません。
最近はLINEやTwitter、InstagramなどのSNS、SMS(ショートメッセージ)を使った詐欺も増えています。
たとえば「あなたのアカウントに不正アクセスがありました」といったSMSや、InstagramのDMで「賞金に当選しました」という偽通知など。
これらもメール詐欺と同じく、リンクに誘導して情報を盗む手口が中心です。
どんな媒体でも「本当に正しい情報か」を自分で確認する姿勢が大切ですよ。
今後の対策に必要な知識と意識
結局のところ、一番の対策は「自分で見抜く力=情報リテラシー」を高めることです。
詐欺の手口は年々進化していて、誰でもひっかかる可能性があります。
「私は大丈夫」と思っている人ほど、危険かもしれません。
定期的にセキュリティに関する情報をチェックしたり、信頼できるニュースや公的機関の情報に目を通すようにしましょう。
家族や友人にも情報を共有して、一緒に防御力を高めていけたら理想的ですね。
まとめ|SBI証券をかたる詐欺メールに注意
| 詐欺メールのポイント5つ |
|---|
| 送信元メールアドレスが公式ではない |
| ドメインがSBI証券と無関係 |
| 不自然な日本語表現 |
| 偽装されたHTMLリンク |
| メールヘッダーに不審なIPやリレー履歴 |
SBI証券をかたる詐欺メールは、公式にそっくりな文面やリンクを使って、私たちを騙そうとしてきます。
この記事で紹介したように、送信元のドメインや文面の不自然さ、リンク先のURLを冷静に見極めることが、被害を防ぐ第一歩です。
万が一クリックしてしまっても、適切に対処すれば被害を最小限に抑えることができます。
詐欺の手口はどんどん進化しており、AIによる文章の巧妙化やSNS型の詐欺も増えています。
公式サイトでの確認や、相談窓口の活用など、正しい知識と冷静な対応を日頃から意識しましょう。
最新のフィッシング詐欺動向については、フィッシング対策協議会の情報も参考にしてください。