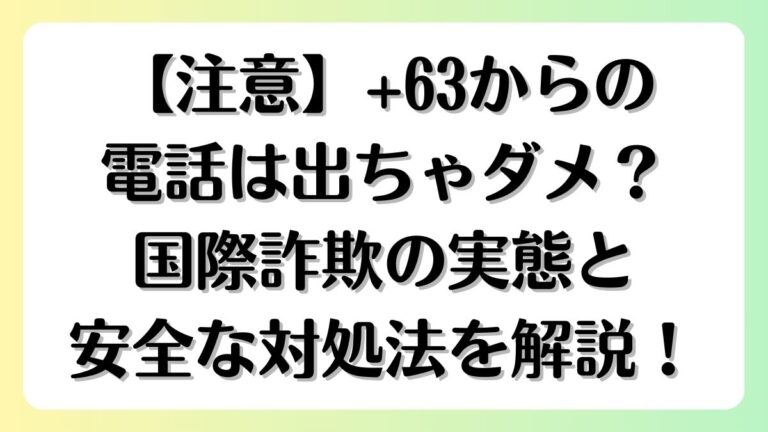「+63」からの電話、出ていいのか迷ったことはありませんか?
この記事では、急増している+63電話詐欺の正体や手口、実際の被害例、そして対策までをわかりやすく解説しています。
「この番号から着信があったけど…どうすればいいの?」と不安になったあなたに、今すぐ役立つ情報を詰め込みました。
この記事を読めば、詐欺の見分け方から安全な対処法までが一気にわかりますよ。
ぜひ最後まで読んで、被害に遭わないための備えをしていってくださいね。
+63電話詐欺の正体と実際に起きている被害例

+63電話詐欺の正体と実際に起きている被害例について解説します。
それでは、順に見ていきましょう!
+63はどこの国?国番号の意味
+63という番号は、フィリピンの国番号です。
つまり、+63から始まる電話は、基本的にフィリピンからかかってきているということになります。
ただし、最近ではこの+63を使った詐欺電話が日本国内でも多数報告されており、実際には海外にいる犯人が日本人を狙って電話をかけているケースが増えています。
不審な点としては、「突然知らない番号からの着信」「折り返すと高額通話料が請求される」などの特徴があります。
知らない国番号の電話には、まず警戒心を持つのが鉄則です。
「なんでフィリピン?」と思うかもしれませんが、国際詐欺グループの拠点の一つであることや、日本語を少し話せる詐欺師がいることも関係していますよ。
最近急増している詐欺の特徴
2024年に入ってから、+63からの不審な電話が急増しています。
その理由としては、日本国内での詐欺対策が強化されたため、海外からの攻撃にシフトしているとも言われています。
最近の特徴としては、企業や行政機関を名乗り「料金の未納がある」といった不安を煽る内容が多く見られます。
特に、SMS(ショートメッセージ)でリンクを送り、フィッシングサイトに誘導する手口が増加しています。
一見すると日本語も整っていて、「本物かも…」と錯覚しそうになることもあるんですよね。
ただ、その裏にはしっかりとした犯罪のシナリオが組まれていて、慌てて対応してしまうとカモになってしまいます。
よく使われる詐欺の手口とは
実際によく見られる手口をいくつか紹介します。
一つは「未納料金がある」と言って金銭を要求するもの。
このとき、実在する宅配業者や携帯会社、電力会社の名前を名乗ることもあり、信用してしまう人も少なくありません。
もう一つは、「お荷物の再配達ができませんでした」などのメッセージにURLを添えて、偽サイトに誘導するタイプです。
そして、最後に「フィリピン在住の知人を装い、LINEやメールに誘導する」といった、やや巧妙なパターンも確認されています。
どれも共通して言えるのは、「焦らせる」「リンクを踏ませる」「個人情報を引き出す」という目的がはっきりしていることです。
冷静になれば違和感に気づける内容なので、まずは落ち着くことが大切ですね。
被害にあった人の体験談
実際に被害にあった方の体験談では、「SMSに記載されたURLを開いた直後、スマホの挙動が不審になった」というケースがあります。
また、「本物の企業だと信じて通話した結果、口座番号を聞き出され、後日不正引き落としにあった」といった深刻な被害も報告されています。
中には、警察に通報したものの、すでに海外のIPを使っているため追跡が難しかったということも。
被害にあった方は、「まさか自分が…」という言葉をよく口にします。
それだけ詐欺の手口が巧妙化していて、どんな人でもだまされるリスクがあるということですね。
「知らない番号=出ない」がいちばんの防御になりますよ。
無視すべきか出るべきかの判断基準
基本的に、+63などの知らない国番号からの電話は無視してOKです。
大事な用件であれば、留守番電話にメッセージが残るはずですし、本当に必要な連絡なら、SMSやメールなど他の手段でも再度届きます。
逆に、こちらから折り返すことで高額な通話料が発生するリスクもあるので、着信履歴が残っていても絶対に折り返さないようにしましょう。
不安なときは、電話番号をネットで検索してみるのもひとつの方法です。
検索すると「詐欺報告あり」などの情報が出てくることも多いです。
とにかく、「慌てず」「焦らず」が大切です。冷静に対応してくださいね。
実際にかかってきたらどうする?対応マニュアル5ステップ

実際にかかってきたらどうする?対応マニュアル5ステップを紹介します。
実際に不審な電話がかかってきたとき、焦らず対処できるように、順番に確認しておきましょう!
電話には絶対に出ない
まず大前提として、知らない国番号からの着信には絶対に出ないようにしましょう。
特に「+63」のような海外からの番号で、心当たりのない相手なら、なおさらです。
一度電話に出てしまうと、相手に「この番号は生きている」と認識され、さらに詐欺のターゲットとして狙われやすくなります。
また、電話を取っただけで会話を録音されたり、声の情報が悪用されるケースも報告されています。
知らない番号に出るのは、まさに“詐欺の入り口”です。まずは着信をスルーしてOKですよ。
留守電・SMSの内容を記録する
着信を無視した場合でも、相手が留守電を残していたり、SMSで何かメッセージを送ってくることがあります。
この内容は、後々警察や消費生活センターに相談する際の証拠にもなりますので、削除せずに保存しておきましょう。
また、SMSの内容にリンクが貼られていることが多いのですが、絶対にクリックしないようにしてください。
万が一開いてしまった場合は、速やかにスマホの設定やセキュリティソフトで確認を取りましょう。
記録があると、状況を的確に伝えられるので、落ち着いてスクショやメモをとってくださいね。
絶対に折り返さない理由
着信が気になって、つい「何か大事なことかも」と思って折り返してしまう方もいるかもしれません。
ですが、これは絶対にやってはいけない行動です。
折り返しの電話をした瞬間に、高額な国際通話料が発生することがあります。
なかには、1分数千円レベルの通話料を請求されるケースもあります。
さらに、折り返したことで「この人はだまされやすい」と判断され、今後も詐欺グループから執拗に狙われるリスクが高まります。
見覚えのない番号に折り返すのは、まさに相手の思うツボです。ぐっと我慢しましょう。
警察や専門機関に相談する
不審な電話やSMSを受け取った場合には、できるだけ早めに警察や各自治体の消費生活センターに相談しましょう。
相談先の一例は以下の通りです。
| 機関名 | 連絡先 | 対応内容 |
|---|---|---|
| 警察(最寄りの交番) | 110番 or 相談窓口 | 被害届の提出、アドバイス |
| 消費者ホットライン | 188(いやや!) | 消費生活センターに自動接続 |
| 国民生活センター | 03-3446-0999 | 被害事例の照会、助言 |
「被害じゃないかも」と思っても、相談して損はありません。早めに動くことで、二次被害を防げることもあります。
「ちょっと聞いてみるか〜」くらいの軽い気持ちでも大丈夫ですよ。
番号をブロック・通報する方法
最後に、かかってきた番号は必ずブロック&通報しておきましょう。
スマホの標準機能でも「着信拒否リスト」に登録すれば、次回からその番号は受信しなくて済みます。
また、Googleや「迷惑電話情報共有アプリ(例:Whoscall)」などで通報すると、他のユーザーの参考にもなります。
もし詐欺と判断できる内容なら、各キャリア(ドコモ、au、ソフトバンク)でも「迷惑SMS通報窓口」が用意されているので、そちらに転送してもOKです。
スマホに届く詐欺のリスクは今後も増えていくと言われていますから、自己防衛として必ずブロック設定を忘れずにしてくださいね。
フィリピンからの国際電話詐欺に共通する特徴
フィリピンからの国際電話詐欺に共通する特徴をまとめてご紹介します。
「詐欺っぽいけどどうだろう?」と感じたときの判断材料として、ぜひ参考にしてください。
未納料金の請求を名乗る
+63からの詐欺電話では、「携帯電話料金が未納です」「電気料金が支払われていません」といった内容が多く見られます。
こうした内容は、突然であればあるほど驚きますし、支払った記憶が曖昧なタイミングを狙ってくるので、とても巧妙です。
しかも、具体的な金額や支払期日まで示されると、つい「もしかして本当かも…」と思ってしまいますよね。
ただし、本当に未納がある場合は、ハガキや書面で通知されるのが一般的です。
いきなり国際電話やSMSで請求してくることはまずありません。冷静に判断してください。
実在する企業名を使う
もう一つの特徴として、詐欺師は「実在する有名企業の名前」を使ってきます。
たとえば、「ヤマト運輸」「楽天」「KDDI」など、日本人にとって馴染みのある会社名を名乗ることで、信頼感を装います。
声やイントネーションに違和感があっても、社名を聞いただけで信じてしまう人も多いのが実情です。
ですが、公式サイトを見れば、詐欺に関する注意喚起がきちんと掲載されていることがほとんどです。
少しでも不安を感じたら、まずは自分でその企業の公式サイトを確認してみてください。
焦らずに、まずは落ち着くことが最強の防御になりますよ。
カタコトの日本語・自動音声
フィリピンからの詐欺電話では、日本語の発音がやや不自然だったり、抑揚がおかしかったりすることがあります。
また、AIのような自動音声で一方的にメッセージが流れてくるパターンも増えています。
自動音声の内容には、「このまま番号を押してください」「再生が終わったらカスタマーに繋がります」など、行動を誘導するものが多く含まれています。
ここで番号を押してしまうと、詐欺グループに「操作に従う人」と認識されてしまい、今後さらに標的にされる危険性が高まります。
違和感のある音声や会話には、すぐに切る勇気が大切です。
SMSと連携した誘導が多い
電話単体ではなく、SMS(ショートメッセージ)とセットで詐欺を仕掛けてくるパターンが非常に増えています。
よくあるのが、「お荷物のお届けに失敗しました」や「料金が未納です。詳細は下記リンクをご確認ください」といった文言と一緒にURLが貼られているもの。
このURLを開くと、偽のログインページや、ウイルスを仕込んだサイトに誘導されるリスクがあります。
中には、本物そっくりに作られたサイトもあって、見分けがつかない場合も。
そんなときは、「まずは開かない」「公式アプリやサイトから確認する」という対応が重要です。
うっかりクリックしても、入力しなければ大きな被害にはつながらない場合が多いです。慌てず、冷静に対処しましょうね。
+63電話詐欺に引っかからないための対策法

+63電話詐欺に引っかからないための対策法について詳しくご紹介します。
大切なことは「知っていること」「備えておくこと」。一緒に対策していきましょう!
着信拒否設定を使う
スマートフォンの機能を使えば、特定の国番号や電話番号をブロックすることができます。
iPhoneなら「設定」→「電話」→「着信拒否設定と着信ID」から、Androidなら「通話設定」→「ブロックリスト」などから設定可能です。
「+63」など、明らかに不審な国番号をまとめて拒否リストに入れておくと安心ですね。
また、迷惑電話としてマークされている番号は、着信時に自動で警告が表示される機種もあります。
こうした機能を上手に使えば、詐欺電話を受け取るリスク自体をグッと下げることができますよ。
詐欺電話対策アプリの活用
スマホユーザーにおすすめしたいのが「迷惑電話ブロックアプリ」の導入です。
代表的なアプリには、「Whoscall」「電話帳ナビ」「トビラフォンモバイル」などがあります。
これらは、不審な電話番号を自動でデータベースと照合して、着信時に警告を出してくれる優れモノです。
中には、ブロックや通報機能まで備えているアプリもあり、設定するだけで日々の不安がかなり軽減されます。
無料でも使える範囲が広いので、まずは1つインストールして試してみるといいですよ!
家族や高齢者に注意喚起する
詐欺被害に遭いやすいのは、スマホの機能に不慣れな高齢者の方々です。
家族や身近な人に、「+63って詐欺電話があるらしいよ」「知らない番号からは出ないようにしようね」と、あらかじめ伝えておくことがとても大切です。
特に、固定電話に国際電話がかかってくる場合は、詐欺の可能性が非常に高いです。
通話録音機能やナンバーディスプレイの活用、詐欺対策グッズ(迷惑電話チェッカーなど)の導入も検討してみてください。
家族全体で情報を共有することで、被害のリスクは確実に減りますよ。
詐欺情報をSNSでシェアする
「こういう電話がかかってきた」「この番号怪しい」などの情報をSNSで発信することも、有効な対策の一つです。
X(旧Twitter)やInstagram、LINEのグループなどで身近な人にシェアすることで、周囲への注意喚起になります。
また、検索した際にその投稿がヒットすれば、同じように悩んでいる人の手助けにもなります。
一人ひとりの声が、次の被害者を救うきっかけになるんですよね。
「これって詐欺っぽい?」と感じたことは、遠慮なく発信してみてください。情報共有が一番の防御になります!
被害にあったときの相談先と対応フロー

被害にあったときの相談先と対応フローについて、わかりやすく解説します。
万が一、詐欺に遭ってしまった場合でも、正しく対処すれば被害を最小限に抑えることができます。
すぐに相談すべき窓口
まず、被害に気づいたらすぐに相談すべき主な窓口を以下にまとめます。
| 相談機関 | 連絡先 | 受付内容 |
|---|---|---|
| 警察 | 110(緊急)または最寄り交番 | 詐欺被害の報告・相談 |
| 消費者ホットライン | 188(局番なし) | 全国の消費生活センターに接続 |
| 国民生活センター | 03-3446-0999 | 専門的なアドバイスや事例共有 |
| 携帯キャリア(ドコモ等) | 各キャリアの窓口 | 通話履歴やSMSの記録対応 |
被害の規模や状況に応じて、複数の窓口に相談するのがポイントです。
「こんなことで相談していいのかな…」と迷わず、早めの行動が安心につながりますよ。
被害届の出し方と必要な証拠
もし金銭的な被害があった場合、警察への「被害届の提出」が必要です。
その際に重要なのが、証拠の確保です。以下のようなものがあるとスムーズです。
- 着信履歴のスクリーンショット
- SMSメッセージの全文
- 相手との通話内容を録音していた場合のデータ
- 銀行口座からの引き落とし記録や振込明細
また、証拠は「時系列」でまとめておくと、より状況が伝わりやすくなります。
警察は情報を集め、同様の手口を追跡していることが多いため、情報提供としても非常に価値がありますよ。
消費生活センターとの連携方法
金銭的な被害に至らなかった場合でも、消費生活センターに相談しておくことで今後の予防策が得られます。
188に電話をかければ、自動的に最寄りの消費生活センターに接続されます。
そこでオペレーターに、どんな内容だったのか、SMSの文面などを伝えると、丁寧に対応方法を教えてくれます。
ときには、悪質な業者に対して警告文を送ってくれることもあります。
「自分だけの問題じゃないかも?」と感じたら、共有の意味でもぜひ相談してみてくださいね。
個人情報が漏れたときの対応
万が一、電話口やリンク先で個人情報(名前、住所、銀行口座、マイナンバーなど)を伝えてしまった場合は、すぐに対処が必要です。
以下に、主な対処方法をまとめます。
| 漏れた情報 | 取るべき対応 |
|---|---|
| 銀行口座情報 | 口座を一時凍結し、金融機関に相談 |
| クレジットカード | カード会社へ連絡して停止・再発行 |
| マイナンバー | 役所に相談して利用停止手続きを検討 |
| 氏名・住所 | 被害が広がらないか定期的に確認 |
情報を渡してしまったからといって、すぐにすべてが終わりというわけではありません。
正しい手順で動けば、被害を抑えることは十分可能です。焦らず、まずは相談から始めましょう。
なぜ+63の詐欺電話が増えているのか?その背景を探る
なぜ+63の詐欺電話が増えているのか?その背景を探ります。
ニュースだけでは見えてこない、背景の深掘りをしていきましょう。
国際詐欺グループの活動が活発化
近年、東南アジアを拠点とする「国際詐欺グループ」の活動が急速に拡大しています。
その中でも、フィリピンは人件費が安く、日本語をある程度話せる人材も確保しやすいため、詐欺拠点として選ばれやすいと言われています。
加えて、法の網をくぐるために「現地の格安SIM」や「使い捨て携帯」を利用して、追跡を困難にする手口も使われています。
日本国内の摘発が強化される一方で、国外からの詐欺行為は捜査や立件が難しく、国際的な協力なしでは防ぎきれないという現実もあるのです。
詐欺電話の裏には、こうした大規模な“犯罪ビジネス”が存在しています。
日本人の情報が狙われている理由
日本人は、詐欺グループにとって「だましやすく」「お金を持っていて」「警戒心が薄い」とされるターゲットです。
特に高齢者層は、電話やSMSに慣れておらず、「相手を疑う」という意識が弱い傾向にあります。
また、日本人はまじめで律儀な人が多いため、「支払っていない請求があります」などの脅しに対して素直に反応してしまいやすいです。
一度でも情報を提供した人は、リスト化されて繰り返し狙われることもあります。
だからこそ、警戒心と情報リテラシーが、最大の防御になるんですよね。
通信網の発達と悪用の仕組み
インターネット回線やVoIP(IP電話)技術の進化により、世界中のどこからでも簡単に日本の電話番号に発信できるようになりました。
これにより、海外からでも日本国内の電話番号を「偽装」して発信することが可能になっているんです。
また、ネット上で簡単に手に入る「電話番号偽装サービス」や「SMS送信ツール」なども、詐欺グループの道具として使われています。
便利な技術が、こうした悪用にもつながっているのが現代の怖いところです。
便利さの裏にあるリスクについて、私たち自身がしっかり理解しておく必要がありますね。
警察が発表した最新の傾向
警察庁やトビラシステムズなどのセキュリティ企業からも、「国際電話詐欺」に関する注意喚起が年々強化されています。
2024年の統計によると、+63(フィリピン)からの着信が迷惑電話の中で上位を占めるようになり、特に「料金未納」や「荷物の再配達」を装った手口が目立っているとのことです。
警察の公式サイトでは、「電話でお金の話が出たら詐欺を疑う」という基本的な考え方を推奨しています。
また、SNSやアプリ上でも、通報情報をもとにリアルタイムで詐欺番号が共有される仕組みが整いつつあります。
情報は常に変化しています。信頼できる機関の発信をフォローしておくと、安心感が違いますよ!
安全に暮らすために知っておきたい詐欺全般の知識

安全に暮らすために知っておきたい詐欺全般の知識を、しっかり押さえておきましょう。
「+63」だけじゃない。日常に潜む詐欺リスクとその防ぎ方、知っておきたいですね。
電話以外の詐欺にも注意
詐欺と聞くと「電話」を想像しがちですが、実はもっと広い範囲で危険が潜んでいます。
たとえば、メール、LINE、インスタのDM、ネット広告、投資勧誘、さらには偽サイトまで…形を変えて次々と出現します。
最近では「パソコンがウイルスに感染しました」と偽の警告を出して、サポート詐欺に誘導する手口も増えています。
詐欺師は“隙”をついてきます。どんな手段にも引っかからないように、疑うクセを身につけておくのが大切ですよ。
フィッシング・なりすましとの違い
「詐欺」とひと口に言っても、その中身はさまざま。代表的なものに「フィッシング詐欺」や「なりすまし詐欺」があります。
フィッシングは、偽サイトやメールを使ってIDやパスワードなどの情報を盗み取る詐欺です。
一方、なりすまし詐欺は、有名人や企業、役所などを装って信用させ、金銭や個人情報を奪う手口です。
+63電話詐欺も「なりすまし型」に該当しますね。
いずれも「本物に見える偽物」を使うのが特徴なので、違和感を感じたらまず疑ってかかることが大事です。
若者や高齢者が狙われる理由
「年配の方ばかりが狙われるんでしょ?」と思いがちですが、実は若者もターゲットになっています。
たとえば、SNSでの“副業”勧誘や、“プレゼント当選”を装った詐欺などは、若年層がだまされる例が多いんです。
一方で、高齢者は電話や訪問販売、詐欺まがいの契約などが多く、手口も異なります。
つまり、年齢関係なく“誰でも狙われる時代”だということ。
家族間で情報を共有しておくことが、最大の予防策になりますよ。
怪しい連絡を受けたらまずやること
もし、怪しい電話やメッセージを受け取ったら、まずやるべきことは「反応しない」ことです。
焦って折り返したり、リンクをクリックしたりする前に、「これって本物かな?」と一度考えてください。
そして、ネット検索や公式サイトを確認し、不審な点があれば即ブロック・通報を。
加えて、家族や知人にも共有しておくことで、まわりの人の被害も防げます。
怪しいと思ったら「行動を止める→調べる→相談する」が鉄則です!
まとめ|+63電話詐欺の注意点を再確認
| +63電話詐欺の特徴と注意ポイント |
|---|
| +63はフィリピンの国番号 |
| 詐欺手口は未納料金や企業名を装うもの |
| 知らない番号には出ない・折り返さない |
| 着信拒否やアプリで事前防止が効果的 |
| 被害時は警察や消費生活センターに相談 |
+63からの電話は、近年ますます増えてきており、その多くが詐欺目的の可能性があります。
知らない国番号からの着信には出ない、個人情報は絶対に伝えないという基本を守ることが最も大切です。
さらに、着信拒否設定や対策アプリ、家族との情報共有など、小さな行動の積み重ねが大きな防御になります。
そして、もし被害や不安があれば、迷わず公的機関に相談しましょう。
正しい知識と備えがあれば、詐欺のリスクは確実に減らせますよ。
最後に、警察庁の公式ページでも最新情報や注意喚起が発信されています。詳細はこちらをご覧ください。